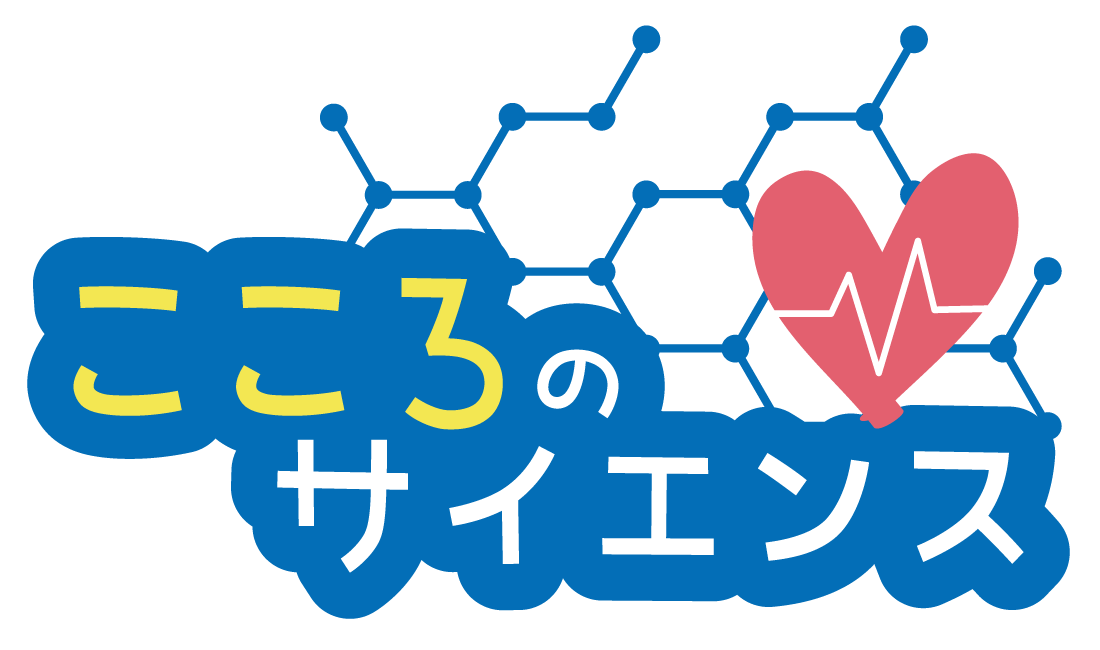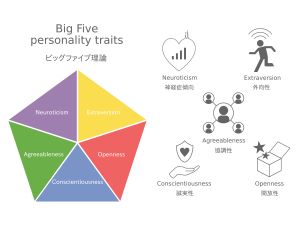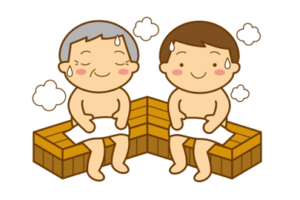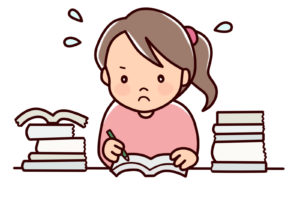新年度の慌ただしさがひと段落し、ふと気が緩む5月になりましたね。新生活で新しい出会いがあった方も多いのではないでしょうか。今回は、「思わず誰かに話したくなる心理学」をご紹介します。
「思わず誰かに話したくなる心理学」
≪カクテルパーティー効果≫
カクテルパーティー効果とは、カクテルパーティーのような騒がしい場所であっても、自分の名前や興味関心がある話題だけはピンポイントで聞き取れる心理効果。音声の選択的聴取や選択的注意とも呼ばれており、イギリスの認知心理学者であるエドワード・コリン・チェリーによって1953年に提唱されました。
≪プラセボ効果≫
プラセボ効果とは、本来薬物としての効果がない錠剤などを「特別の効果をもつ薬である」と伝えて与えると、暗示的な作用が働くことで、説明された通りの効果が得られることであり、別名、偽薬効果ともよばれています。薬だと思って飲んだら、ただの小麦粉でも効いちゃうことがある現象。病は気からといいますが、思い込みも大切ですね。
≪バーナム効果≫
バーナム効果とは、誰にでも当てはまる一般的な特徴や説明を「自分だけに当てはまる」と勘違いしてしまう心理現象のこと。心理学者のバートラム・フォア氏が検証したことから、「フォアラー効果」とも呼ばれています。バーナム効果には、自分にとって都合のよいことを信じる心理現象「確証バイアス」が大きく影響すると考えられています。
占いなどで「あなたは時々落ち込みますが、基本的には前向きです」など誰にでも当てはまることを「当たってる!」と思ってしまう。ついつい信じてしまいますが錯覚なのですね。
≪返報性の原理≫
返報性の原理とは、相手から何かを受け取ったときに「こちらも同じようにお返しをしないと申し訳ない」という気持ちになる心理効果のことです。試食をもらうとつい買いたくなる、値引きをして貰ったから買わないとなど、筆者もよく、買うつもりはなかったのに買ってしまった経験があります。
≪ジャムの法則≫
ジャムの法則とは、選択肢が多すぎると逆に選べなくなる心理のことです。決定回避の法則ともいいます。
≪ランチョン・テクニック≫
新しく人間関係を築く時、相手に好意を待って欲しい、お願い事を聞いて欲しいなど、相手とぎゅっと距離を縮めたい時にオススメなのが「ランチョン・テクニック」です。アメリカの心理学者のラズランは、食事中に聞いた話は好意的に受け取られやすい事を示し、「ランチョン・テクニック」と名付けました。食事を共にする、いわば「同じ釜の飯を食う」ことは、ビジネスの席ではもちろんのこと、恋愛でも効果を発揮するようで、大皿料理をシェアし、さらにその料理の味などの感想を述べ合うといいとされています。「ランチョン・テクニック」は食事の席だけではなく、飴やガムなどでも同じ効果が期待でき、打ち合わせの席などで美味しいコーヒーやちょっとした軽食を出してコミュニケーションをとるのも効果的のようです。
最後に
いかがだったでしょうか?心理学には思わず笑ってしまうような、人間の不思議でユニークな行動や思考パターンがたくさんあります。ぜひ仲良くなりたい人と食事をしながら、会話の小ネタにしてみてくださいね。

参考サイト
●【宝島社】大人の心理学常識「手っ取り早く人と仲良くなる方法」
●【こころ検定】~少し変わった視点から心理学を考える Part5~
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo