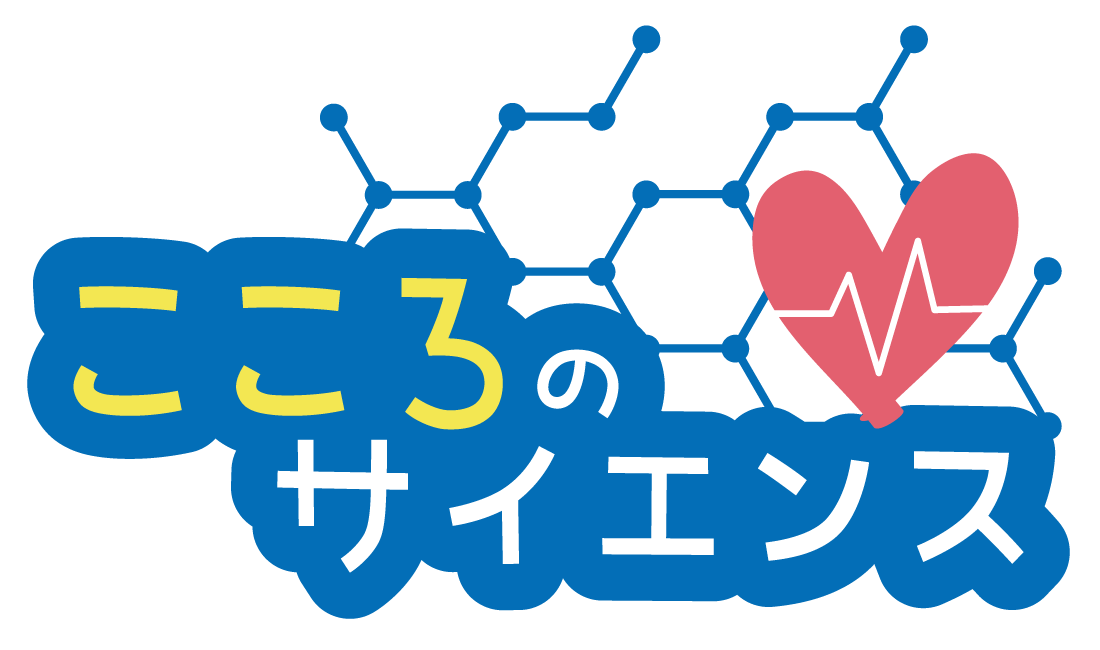仏教と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
7月27日は「そろばんの日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。7月27日を含む、毎月27日は「仏壇の日」に制定されています。これは、全日本宗教用具協同組合(全宗協)が制定したものです。685年の3月27日(旧暦)に天武天皇が「諸國(くにぐに)の家毎に佛舎(ほとけのみや)を作り、即ち佛像と経とを置きて礼拝供養せよ」との詔(みことのり:天子の命令)を出したとされています。これは、奈良時代に成立した日本最古の歴史書である「日本書紀」に記述されており、ここから、私たち日本人は仏壇に手を合わせて拝むようになったとされています。これがきっかけとなり、3月27日(新暦)が「仏壇の日」となり、その後、この習慣が毎月27日に拡大されました。
「仏壇の日」にちなみ、名古屋の仏壇商工協同組合では、毎年3月27日の「仏壇の日」に大須観音で仏壇供養祭を行っており、古い仏壇を供養・焼却しています。
では、仏教と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
東洋的心理療法とは
心理学には東洋的心理療法という領域・分野があります。これは、東洋に伝わるヨガや禅などの修行法の技法や考え方を取り入れたり、それらと共通する特徴を多く有する心理療法の総称です。従って、文教的な要素も多いものとなっています。具体的には、森田療法や内観療法など日本で開発されたものでもありますが、自律訓練法なども、その成立の過程にヨガや禅の影響が認められる心理療法は欧米にも多く、それらも含めるべきであると考えることができます。東洋的心理療法の特徴として、以下のようなものがあります。
- 精神疾患の治療・支援だけでなく、健康の増進や人間的成長を目的とする
- 一定の訓練課題の実践を治療・支援の枠組としている
- 体験を通じた自己変革を進めるセルフ・コントロール法である
- 身体の動きや身体感覚への気づきが重視されている
- 集団療法のシステムを活用できること
従って、来談者中心療法におけるフォーカシングやゲシュタルト療法などの、人間性心理学やトランスパーソナル心理学において用いられる心理療法にも、これらの特徴を有するものが多くあり、広い意味で、これらも東洋的心理療法と捉えることもできます。
また、ヨガや座禅などが心理療法の技法として直接用いられることもあります。これらは、主に心身医学の分野で心身の弛緩法あるいは調整法として、または、洞察や至高体験の誘発法として様々な瞑想法が活用されています。最近では、マインドフルネスなども、瞑想や禅の要素が含まれた心理療法として注目を集めています。
瞑想法とは
東洋的心理療法でも重要な位置を占めるのが瞑想法です。これは、非常に仏教的な要素が強いものとなっています。瞑想法とは、そもそも、ヨガ・禅・チベット仏教・キリスト教などにおける様々な行法の総称として用いられている用語です。瞑想法の多くに共通するのは、静かに座った姿勢で何らかの対象に注意を集中する方法をとります。また、ポーズをとるもの、身体を動かすものも瞑想法と見なされています。また,注意を向ける対象も、呼吸や心の動きなど多種多様であり、技法の手続は実に様々です。
瞑想法が東洋以外の西洋に普及していく際に、仏教的な部分、つまり、宗教的背景を切り離して技法のみが広まりました。その結果、瞑想法という手続の心身への影響に関する生理学的な研究(科学的・論理的・数学的)が進められました。瞑想法は心理的な意識の変容状態をもたらし、生理的には弛緩反応を生じさせることが確認されており、1970年頃から心理療法の技法として用いられるようになっています。
日本をはじめとする全世界で主流となっている認知行動療法の第3の潮流となっているマインドフルネスは、瞑想法の要素が含まれており、科学的な根拠もしっかりとあるものとなっています。また、治療・支援だけではなく、再発防止という観点からも発展が進んでいます。
最後に
このように、仏教の要素は、心理療法の中にも多く含まれているものとなっています。
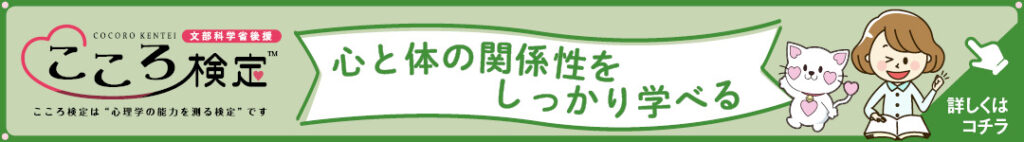
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo