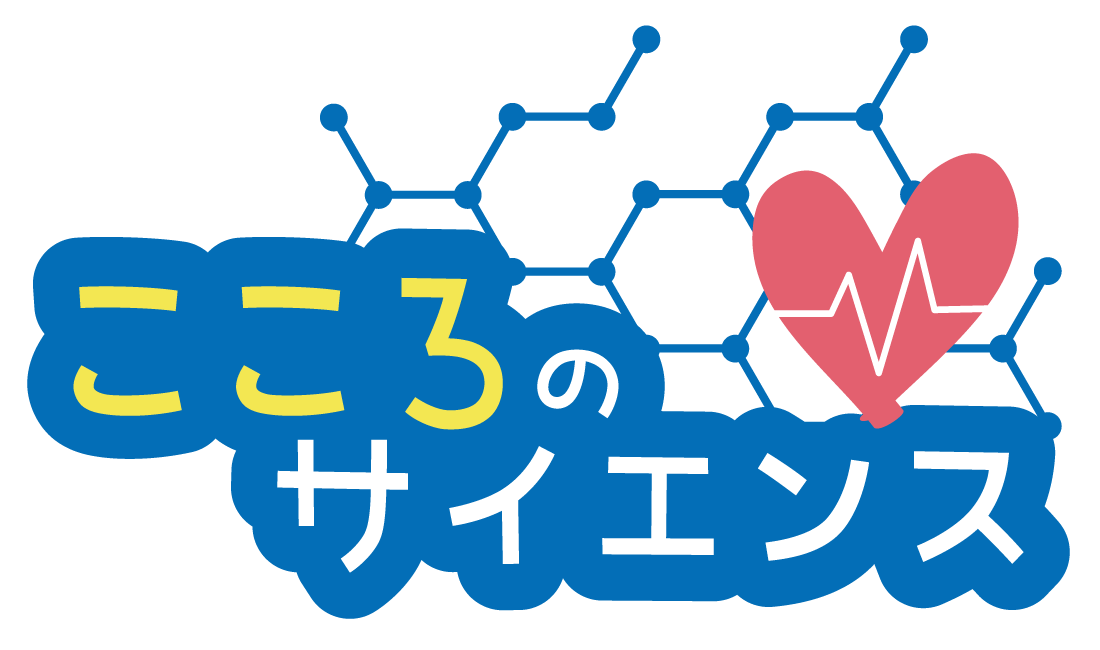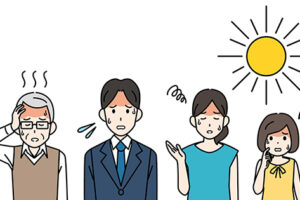スチュワーデスの日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
3月5日は「スチュワーデスの日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。3月5日は「スチュワーデスの日」に制定されています。これは、1931年3月5日に東京航空輸送社が実施した日本初のスチュワーデス採用試験の結果が発表されたことに由来しています。当時はエアガールという呼び名で募集され、2月5日に試験が実施され、140人の応募に対し、合格者は3人という狭き門でした。そもそも、スチュワーデスとは、旅客機に乗り込み接客サービスを行う女性客室乗務員のことで、船舶の司厨員に由来するスチュワードの女性の呼称です。現在は性差のない呼称であるキャビンアテンダントやその略称であるCAと呼ばれることが多くなっています。また、日本語では客室乗務員という言葉が正式とされるようになっています。
では、スチュワーデス・キャビンアテンダント・客室乗務員と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
感情労働について
心理学において、感情労働に関する初期の研究が客室乗務員を対象としていたという記録があります。私たちは職業上の必要性から、自身の感情をコントロールするということを“仕事”・“労働”として実施することがありますが、これを感情労働とよびます。感情労働は従業員が自身の感情を使用・コントロールすることでパフォーマンスを発揮するものです。感情労働における感情のコントロールは、従業員が所属する企業・組織にとって望ましい感
情を生起させることであり、これは必ずしも従業員自身の内的な状態とは一致しないことも多いです。例えば、顧客を喜ばせる・楽しませるということが業務上必要となった場合、対応する従業員自身の中で“喜”や“楽”などの感情が実際に生起していなくても、笑顔を作ったり、声を出して笑うことがあるかと思います。
また、企業・組織や従業員自身には何の過失も無かったとしても、顧客から謝罪を要求された場合、対応する従業員自身の中で実際に罪悪感や後悔などの感情が生起していなくても、頭を下げて謝罪したり、声のトーンを落として会話をしたりすることもあるかと思います。さらには、顧客からの理不尽な要求に対して、従業員自身が本当は怒りを感じていたとしても、表情や声に怒りが滲み出るのを抑え、平静な対応をすることもあるかもしれません。これらは全て感情労働に該当するものであり、従業員の感情を一種の“商品”として扱い、感情を“販売”するということなのです。
感情的不協和について
感情労働は自らの実際の感情とは異なる感情の生起や、実際の感情と一致しない行動・態度を生起させることになるため、感情の葛藤状態である感情的不協和を引き起こす場合が多いとされています。感情的不協和は心理的な不快感をもたらすものであり、ストレッサーとなるものです。従って、感情労働に従事することで、心身の不調や仕事に対する満足度の低下などが発生することがあります。感情労働は従業員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性を含んでいますが、業務の関係上、感情労働を一切実施しないということが困難な従業員は多いと考えられます。また、従業員自身は自分の携わっている業務が感情労働であるということを自覚しておらず、心身への影響についても正確に認識していないことも多いです。
そして、感情労働と関連の深いものとして、バーンアウト(燃え尽き症候群)があります。バーンアウト(燃え尽き症候群)は主に産業場面における仕事上の問題として、心身両面の疲労やモチベーションの低下、作業能率の低下、自他に対する否定的感情や態度の発生などを伴う状態のことを指します。バーンアウト(燃え尽き症候群)はあくまで状態を示すものであり精神疾患ではありませんが、特に近年の産業場面で問題となっています。
最後に
研究の結果、バーンアウト(燃え尽き症候群)は客室乗務員などの対人サービスを主とする業種や、慢性的に高いストレスに曝される業種に多いとされています。これらの業種は感情労働に従事している場合が多く、感情労働による感情的不協和はバーンアウト(燃え尽き症候群)と関連が強いことが分かっています。
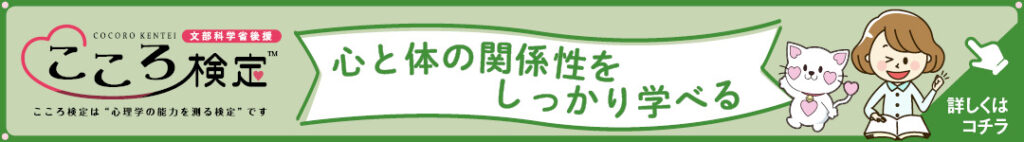
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo