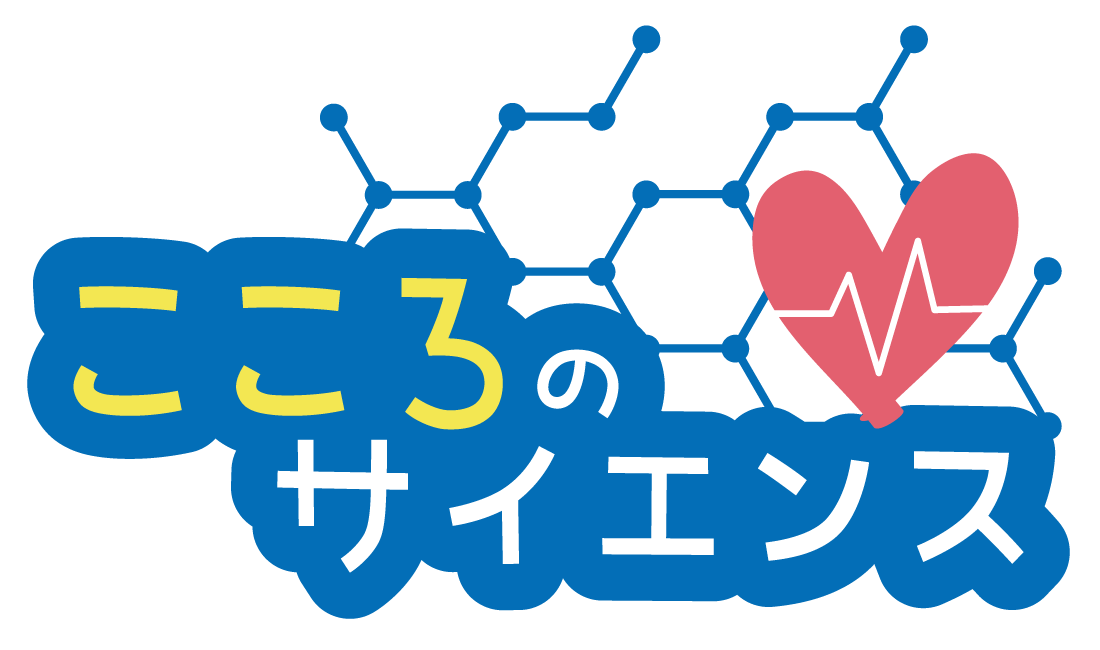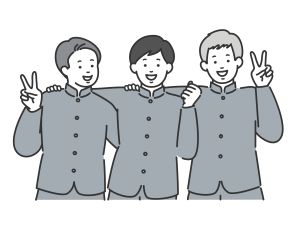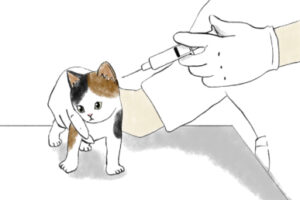国際フレンドシップ・デーの日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
7月30日は「国際フレンドシップ・デー」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。7月30日は「国際フレンドシップ・デー」に制定されています。これは2011年7月の国連総会で制定された国際デーの一つであり、英語表記は「International Day of Friendship」となります。この日は国や文化を超えた友情が世界平和を促進することを想起する日であるとされています。国連はこの国際デーを通して、政府や国際機関、市民社会グループが、相互理解や和解に向けた対話を促進するための取り組みやイベントを実施することを奨励しています。現在、世界は貧困や暴力、人権侵害など多くの課題に直面しており、これらは世界の人々の平和や安全、社会的調和を損なうものとなっています。そこで、これらの問題に対する根本的な原因の対処には人間の連帯という共通の精神、つまり最も単純な友情であると考えられます。
そして、友情が強い信頼関係を築くことのベースとなり、永続的な安定を実現するための変化や、より良い世界への情熱や団結を生み出すことができ、全ての人々の安全や安心に貢献することになると考えられています。 国際フレンドシップ・デーは世界中の様々な国で実施されており、日付は国によって様々です。パラグアイは7月30日、ブラジル・アルゼンチンは7月20日、アメリカは2月15日となっており、日本では前述の通り7月30日となっています。
では、友情と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
子どもの友人関係・仲間集団がもつ重要性について~発達心理学~
発達心理学において、子どもの友人関係に関する研究が実施されています。心理学においては友人という用語よりも「仲間」という用語で表現することが多いです。仲間(peer)とは同等性(年齢や社会的立場等)と互恵性を備えた横の関係であると定義されています。そして、年齢や性別に応じて仲間の影響力や形成要因が変化することが研究の結果、判明しています。幼児期から児童前期の子どもの場合は家が近い等の空間的な相互接近が仲間の形成要因となりやすいとされています。また、児童後期から中学1年生くらいまでは「何となく好き」であるとか「優しい」といった同情愛着が原因として大きいとされています。さらに,児童期から思春期、青年期へとパーソナリティ特性の尊敬や性格、趣味、意見の共鳴による結びつきが強まるとされています。そして、何かを一緒にするという協力行動については、児童後期から青年期、成人期にかけて、協力行動は増加していくとされています。
友人関係や仲間集団が持つ重要な要素として、社会性の獲得が挙げられます。社会性とは生まれてから社会の成員になるまでの過程で身につけていくものであるとされており、人間関係を形成したり、人間関係を円滑に維持する能力であるとされています。発達心理学では、社会性を「対人行動(他者に対して適切な対応ができること)、集団行動(集団の中で協調的に行動できること)、社会的要求(仲間から好意を受けたいという欲求を持つことや仲間として認められたいという欲求をもつこと)、社会的関心(時代の情勢、風潮に関心を寄せること)などが挙げられます。社会性が獲得されるメカニズムとして、誰かのマネをしていくことで必要な事や正しい事を学習・獲得していく模倣、自身と他者を「同じ」と感じて態度や行動を形成させていく同一視、学習心理学における刺激と反応の関係性を観察によって獲得していく観察学習、発達心理学的な愛着等に獲得など、様々な事例があると考えられています。
最後に
このように、心理学では友人や仲間という概念についても様々な角度から研究が実施されているのです。
友人や仲間については、こころ検定3級の第1章でも概観していますので、興味・関心のある方は、是非、勉強してみていただければと思います。
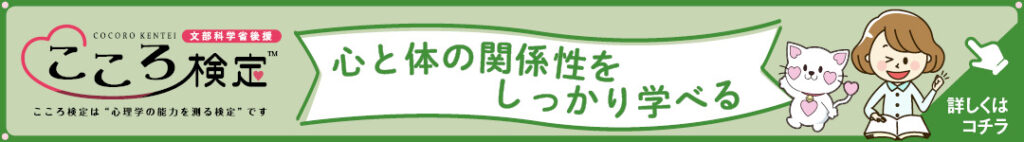
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo