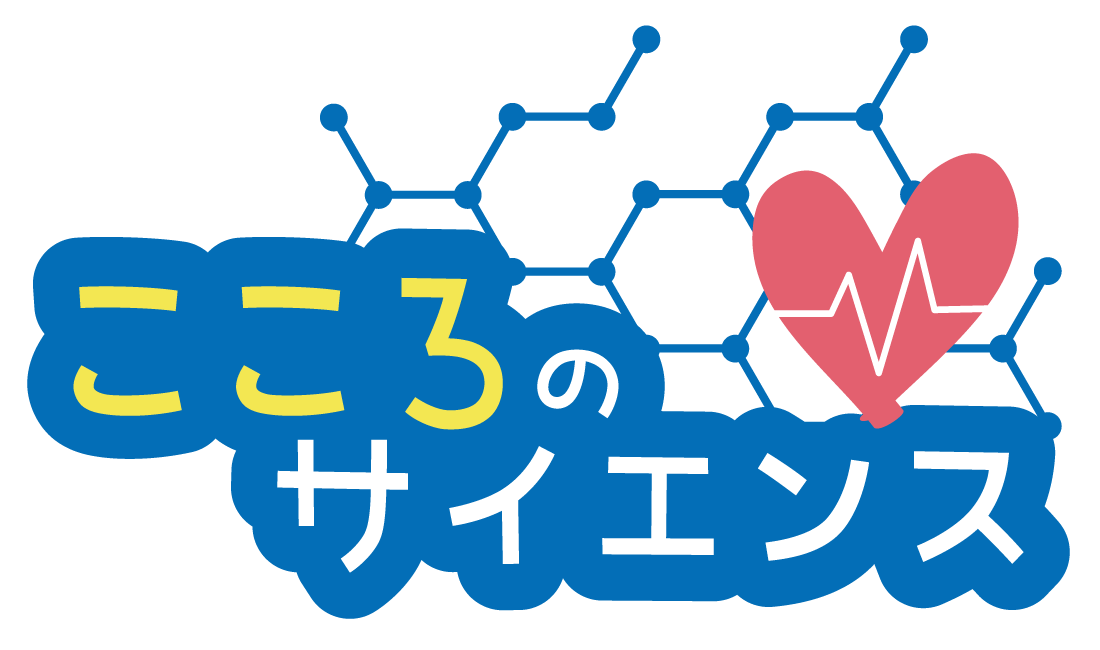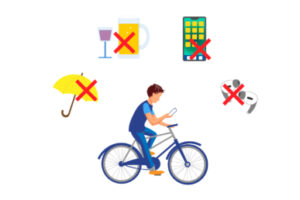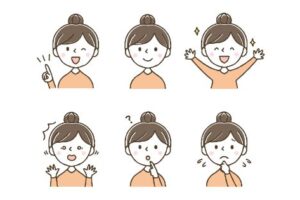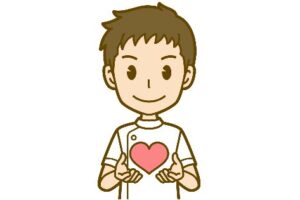ふくの日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
9月29日をはじめとする毎月29日は「ふくの日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。9月29日をはじめとする毎月29日は「ふくの日」に制定されています。これは株式会社 日本アクセスが制定したものです。日付の由来は幸福な気持ちの福を「ふ(2)く(9)」の語呂合わせからきています。日本アクセスは食品会社であるため、この日は一年を通じて様々な季節の食材や景色を取り入れた商品があり幸福な気持ちになれる和菓子の魅力を伝えることで小売業の和菓子の販売促進企画を進めることが目的となっています。なお、2月9日は同社が制定した「大福の日」、魚の河豚(ふぐ)を記念した「ふくの日」、5月29日は「幸福の日」、12月29日は「福の日」となっています。同社では毎月29日の「ふくの日」、2月9日の「大福の日」に合わせて、消費者キャンペーンを実施したり、マンネリ化しがちな和菓子売場の活性化を促し、売上拡大を図っていたりしています。
では、心理学と幸福には、どのような関係があるのでしょうか。
主観的幸福感について
心理学では主観的幸福感(Subjective Well-Being, SWB)、もしくは日本語でウェル・ビーイングという概念が研究されています。これは、あくまで主観的に本人が「自分は幸福か?」ということをどのように捉え、感じているのかというものです。主観的幸福感は感情的な側面やポジティブな感情の量、ネガティブな感情の量、人生に対する認知的側面(人生観など)によって構成されています。そして、基本的には一時的なものではなく、長期的なものです。また、メンタルヘルスの観点からも主観的幸福感は重要なポイントとなっています。うつ病などの精神疾患のクライエントは主観的幸福感が非常に低いことが判明しています。
そして、主観的幸福感は私たちの日常生活にも様々な場面で影響を及ぼしています。たとえば、主観的幸福感が高い人は積極的に行動し、新しいことにも前向きに取り組む傾向があります。また、物事をポジティブに捉える、難しい状況においても柔軟に対処することができます。生理心理学的な観点では、免疫力が高く、心臓病や糖尿病などの生活習慣病リスクも低く、コルチゾールなどのストレスと関連の深いホルモン分泌も低いことが判明しています。さらに、社会性やコミュニケーションでいえば、他者との関係を円滑に保ち、信頼関係を築きやすく、親切で共感的な態度を示すことが多くなります。そのため、周囲からのソーシャル・サポートも得やすくなります。
QOL(生活の質:クオリティ・オブ・ライフ)について
幸福感に関する指標として、主観的幸福感の他にもう1つ重要な概念として、QOL(生活の質:クオリティ・オブ・ライフ)というものがあります。QOLは心身医学の現場で活用されることがあり、医療現場や心理カウンセリングの現場でも利用されています。QOLは私たちの送っている生活の向上についての評価基準となるものです。QOLは、物質的な豊かさだけでなく総合的に判断されるものです。物質的な豊かさは、収入や資産についての金銭的指標によって測ることができますが、それがそのまま、私たちの生活における満足度や幸福度に直結するわけではありません。QOLは私たちの消費に関する意識や行動を検討する際に利用されることもあります。また、医療や福祉のサービスのあり方を考える上でも、重要性の非常に高いものとされています。精神疾患のクライエントに対する心理アセスメントとして、抑うつ・不安などの低下・減少を確認することが多くあります。
一方で、身体疾患に伴う精神的苦痛、慢性疾患の治療長期化に対する不満、外科的外傷後のリハビリによるストレス、高齢者の各種能力低下や疾病頻度増加に伴う日常生活への影響などについては、的確なアセスメントが困難なことが多いとされています。たとえば、糖尿病の場合、血糖状態の良好さが病気の改善の指標となるが、血糖状態が良好であっても、生活における自己管理の困難さ等に対して苦痛を感じている患者も多く、必ずしも「血糖状態が良好 = 心身ともに健康」ではないということになります。
従って、疾患そのもの改善・治癒の評価とは別に、疾患から派生する心理社会的な問題の改善についても評価しなければ、患者が「真の意味で健康」であると判断することは困難となります。そこで、疾患の改善・治癒の評価と並行して、特に心身医学等の現場では、QOLを総合的な健康状態の指標として用いることが多くなっています。例として、めまいを発症している高齢者、人間ドック利用者、終末期ガン患者などに対して、医学的な治療・支援の効果量とは別に、患者の「真の健康」についてQOLを測定することで評価するということが実施されています。
最後に
このように、心理学や精神医学では主観的幸福感やQOLという観点から、幸福感について研究が進められています。
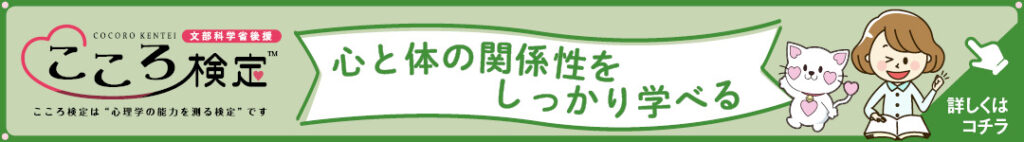
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo