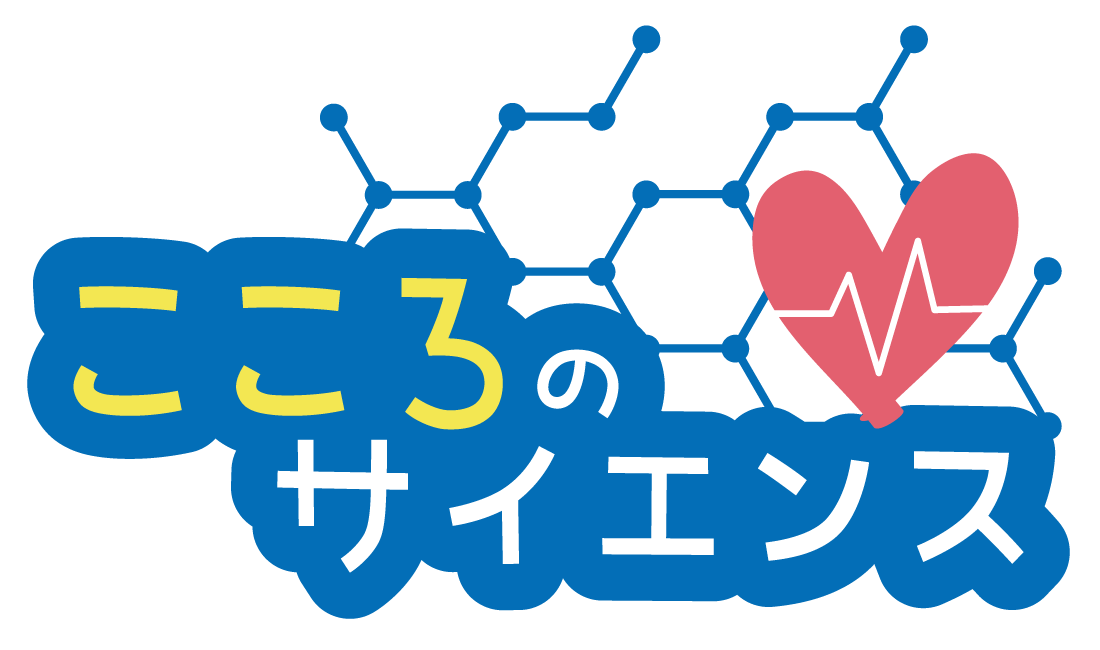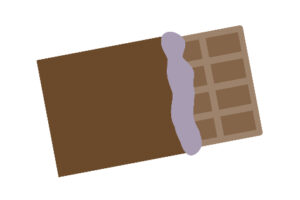前回、キューブラー・ロスが提唱した、死への受容のプロセスについてお伝えしました。
この理論は海外の精神科医の持論であり、日本人の死への受容プロセスとは少し異なるようです。
今回は、柏木哲夫が提唱した「死にゆく患者の心理プロセス」についてご紹介したいと思います。
- 【希望】回復や自分の病状や予後への希望を持つ
- 【疑念】希望を抱いているにも関わらず、病状が良くならないことへ疑念を持つ
- 【不安】その疑念に対し、不安が起こる
- 疑念や不安を尋ねる人→その疑念に対して答えが得られなければ④【いらだち】→⑤【うつ状態】
- 疑念や不安を尋ねない人→⑤【うつ状態】へつながる
- 【いらだち】
- 【うつ状態】
- 【受容とあきらめ】受容→積極的に死を受け入れる。
- 本人と看取る側との間に人間的連続性が存在し、看取る側に心のさわやかさが残る。
- あきらめ→消極的態度。絶望感。放棄。看取る側にはもやもやしたものが残る。
①で抱いた回復への希望は、死の直前まで持ち続けるのだそうです。

日本人には病状や予後を尋ねない人のほうが多く、その理由として以下の6つがあります。
- 防衛(尋ねることが怖い)
- 否定(死や病の否定)
- 自制(不安はあるがそれをおさえる)
- 遠慮(尋ねては申し訳ない)
- 不信(患者とスタッフ間のコミュニケーションがとれていない場合など)
- いたわり(自身の病状が思わしくないことやそれを周囲が隠していることに対して気づいていながらも他者へのいたわりから黙っておく)
日本人の性格傾向として、思慮深さや周囲への気遣いなどが挙げられることがあり、④遠慮や⑥いたわりについて何となくそうかもな、と感じるところもあり、自分が死に向かい合わなければならないときに、果たして他者への気遣いまで出来るのか、きちんと受容できるのかとも考えさせられました。
参考文献 はじめての臨床心理学 森谷寛之・竹松志乃 編著 1996 北樹出版

著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo