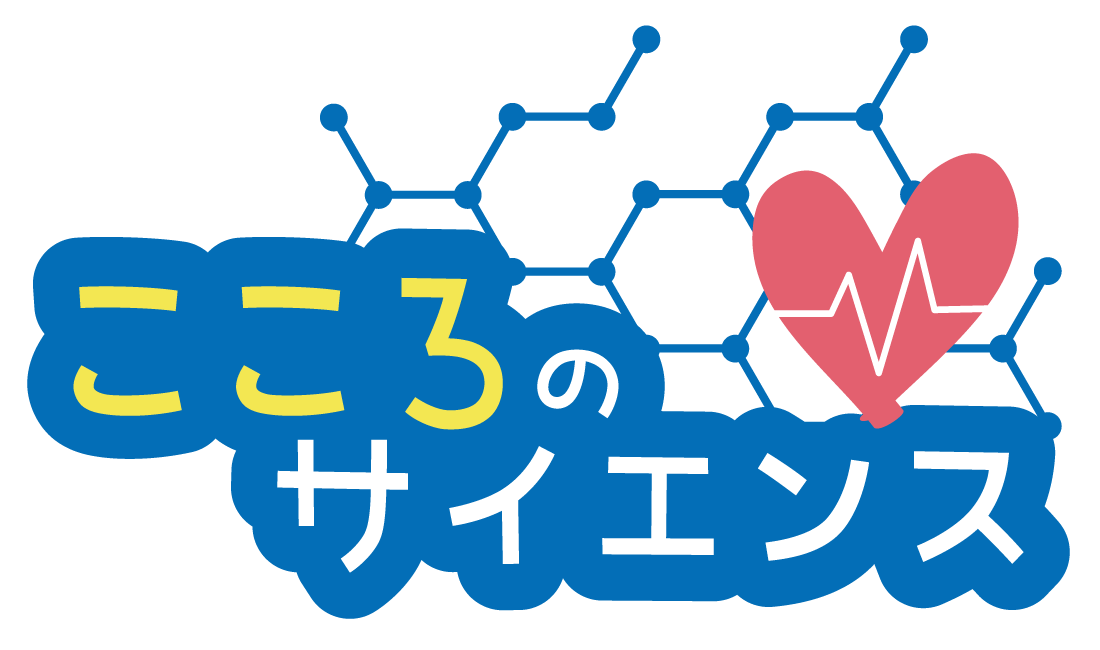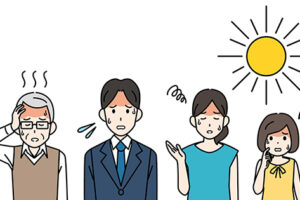盗難防止の日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
10月7日は「盗難防止の日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。10月7日は「盗難防止の日」に制定されています。これは一般社団法人・日本損害保険協会が制定したものであり、日付の由来は。「とう(10)なん(7)」(盗難)の語呂合わせからきています。この日は家屋侵入盗難・自動車盗難などの盗難被害を防ぎ、これらの窃盗犯罪をなくすことを目的としてた啓発運動などが行われています。
では、盗難と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
日本における窃盗犯罪の現状と防犯心理学の取り組み
まず、日本における窃盗や盗難などの犯罪被害の現状として、犯罪件数全体の約7割が窃盗であるということが報告されています。窃盗犯罪は「何がどのように盗まれたのか?」によって分類されており、自転車窃盗、万引き(非侵入型窃盗)、特殊詐欺関連の払出盗(偽キャッシュカードなどを悪用したATM現金窃取)、職権盗(公務員を装って盗みを働く手口)、金属やケーブルなどの金属盗難などがあります。
そして、窃盗や盗難などの犯罪については、犯罪心理学の分野で研究が進められています。特に日本では防犯的な要素が強い研究が多く実施されています。代表的なものとして、防犯環境設計(CPTED:Crime Prevention Through Environmental Design)というものがあります。これは環境を意識した防犯対策であり、建物や街区の構造・景観を工夫することで、犯罪者の「捕まるかもしれない」という認知を引き起こさせることで、犯罪の心理的抑止を高めるというものです。具体的には、街頭や照明を工夫する、人の視線を意識した窓の配置、建物間の境界線の明確化、逃走経路の遮断、多数の防犯カメラの設置と死角の排除などがあります。 アメリカで実施された犯罪心理学の研究において、これら防犯環境設計(CPTED)によって窃盗や強盗が約30%以上減少したという報告もあります。
日本における窃盗・盗難の実態と心理的要因の分析
また、犯罪心理学では被害者の観点からも窃盗や盗難について研究が実施されています。特に日本では犯罪報告率が低いという背景があります。これは犯罪被害を報告することを恥じる傾向が強い事や迷惑をかけたくないという意識が強いことが関係していると考えられます。そのため、実際には盗難被害があったにもかかわらず、警察に届け出ていないケースも多いと考えられており、そもそもの警察白書等の公的な統計データよりも多くの犯罪が発生している可能性もあると考えられます。
なお、そもそも、欧米などの諸外国と比較して、日本の犯罪発生率は低い数値を維持してることも報告されています。これは地域コミュニティの規範や相互監視が強固であることが関係していると考えられます。
もう1つ、窃盗や盗難については精神医学の観点からも研究と治療・支援が実施されています。精神疾患の一種に窃盗症(クレプトマニア)とよばれるものがあります。一般的な窃盗が「お金がなくて買えないから盗んでしまおう」という窃盗する側に何らかの利益を得ることが目的となっています。一方で、窃盗症(クレプトマニア)の場合はお金がないわけではなく、普通に商品を購入することができるにもかかわらず窃盗をしてしまうというものです。また、数百円程度の少額の商品の窃盗を繰り返すこともあり、さらには窃盗した物自体にはあまり興味・関心を示さないという特徴もあります。そのため、窃盗後に盗んだ物を放置したり、一度も使わずに捨ててしまったりしてしまうこともあります。窃盗症(クレプトマニア)は世界的な精神疾患の診断・統計マニュアルであるDSMにも掲載されており、秩序破壊的・衝動制御・素行症群の中の反社会性パーソナリティ症の下位分類に位置づけられており、明確な診断基準も定められています。
最後に
このように、心理学や精神医学では窃盗や盗難などの犯罪についても、様々な角度から研究が実施されているのです。
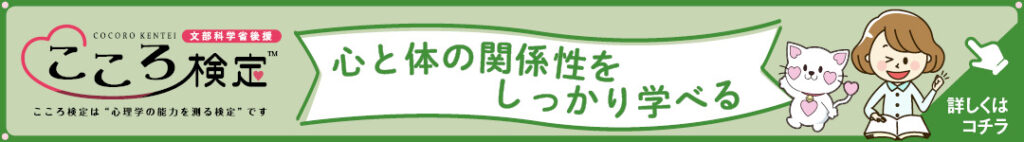
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo