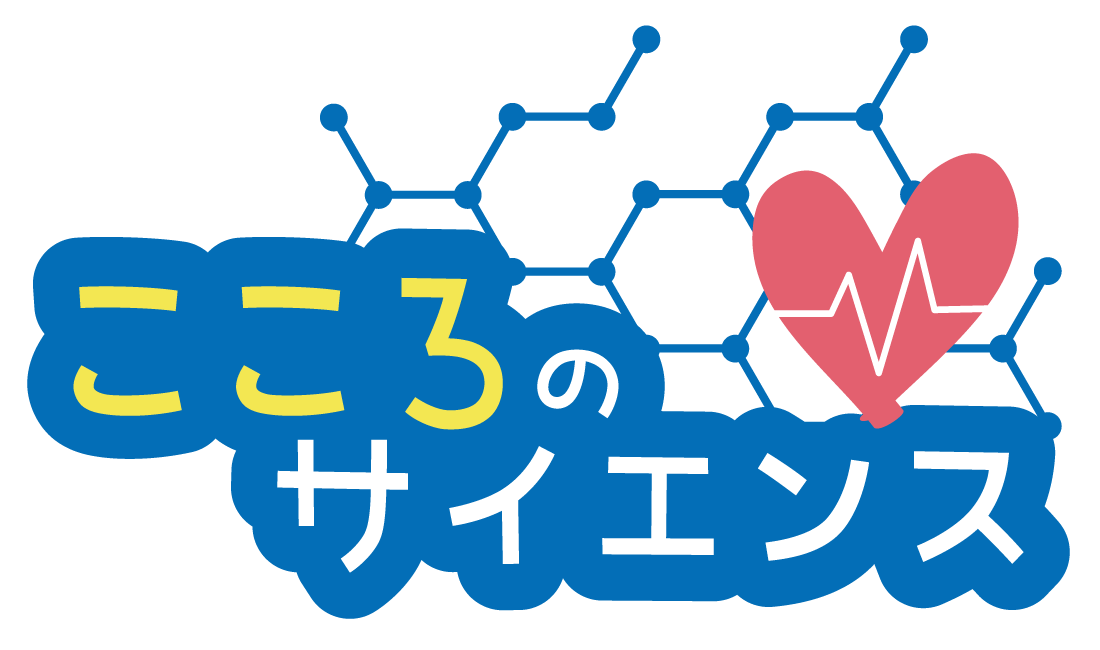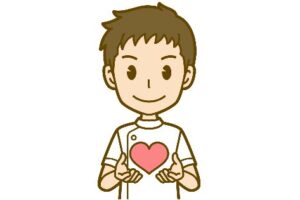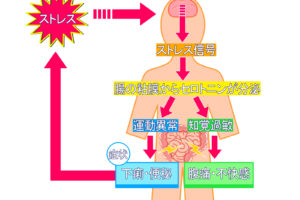家族と暮らす動物の幸せを考える日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
4月29日は「家族と暮らす動物の幸せを考える日
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。4月29日は「家族と暮らす動物の幸せを考える日」に制定されています。これは、パナソニック株式会社と株式会社朝日新聞社が制定したものです。日付は犬や猫のシンボルの肉球に由来して4月29日を「よい(4)にくきゅう(29)(よい肉球)」と読む語呂合わせが由来となっています。パナソニックはは動物保護団体への商品の寄贈、保護犬・保護猫の譲渡会の開催などの社会貢献プロジェクトに従事し、ペットと飼い主の健やかな暮らしをサポートする商品の開発も実施しています。また、朝日新聞は犬と猫の飼い主向けのウェブサイト「sippo」(シッポ)を運営しており、人間とペットが共生できる社会づくりに取り組んでいます。このようにペットに関する社会的な活動を実施している2つの会社が家族の一員であるペットの幸せを願い、記念日を通して家族と暮らす動物の幸せを多くの人に考えてもらうのが目的となっています。
では、ペットを飼うということと、心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
ペットを飼う ~メンタルヘルスとQOR~
心理学、特にメンタルへルスにおいて、ペットを飼うということはQOL(クオリティ・オブ・ライフ)と関連があるとされています。QOL(クオリティ・オブ・ライフ)とは、人間の生活の向上についての評価基準の代表的なものの1つです。QOL(クオリティ・オブ・ライフ)は物質的な豊かさだけでなく、総合的に判断された生活の質のことを指します。物質的な豊かさは、収入や資産についての金銭的指標によって測ることができますが、それがそのまま、私たち人間の生活における満足度や幸福度に結びついているわけではありません。たとえば、人それぞれの価値観に沿った活動をどの程度行うことができるか等によって、満足度等は大きく変化する可能性があります。そして、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)に影響する要因を探索することが、私たち人間の消費に関する意識や行動を検討する際に中心となる課題の1つであると考えられます。また、医療や福祉のサービスのあり方を考える際にも重要性は非常に高く、物質的な要因に加え、認知的・感情的・行動的などの心理的な要素においても重要となっています。
ペットを飼うということは、私たちのメンタルへルスにとって、前述のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上や維持にポジティブな影響を及ぼすものであるとされています。一方で、ペットが亡くなってしまうこともあります。これは、ペットロスとよばれる状態であり、メンタルへルスにネガティブな影響を及ぼすものであるとされています。ペットロスはペットと共に過ごす事によって培われた深い愛着や愛情が、突然、ペットに死が訪れたことによって心の行き場を無くしてしまうことによって、引き起こされる精神状態であるとされています。
ペットロス・ハートケアとは
そして、ペットロスに関して、メンタルケア学術学会が関連している資格として「ペットロス・ハートケアカウンセラー」という資格があります。この資格では、ペットとの生活について、ペットと人間の歴史、そして、ペットロスの基礎概念について学習します。さらに、心理カウンセリングの基礎知識、心理療法の基礎知識、基礎心理学、発達心理学、社会心理学などについてもカリキュラムに含まれています。また、精神医学の分野として、精神疾患の基礎知識、メンタルヘルスと脳の仕組み(生理心理学)、人間の身体について(解剖生理学)、感情と感覚について(感情心理学・知覚心理学)などについても学習範囲に含まれています。そして、情動やストレス、健康とQOL(クオリティ・オブ・ライフ)に関しても学ぶこととなっています。
最後に
このように、ペットにまつわる心理学的な要素はQOL(クオリティ・オブ・ライフ)だけでなく、ペットロスというメンタルへルスとの関係についても様々な活動が実施されています。
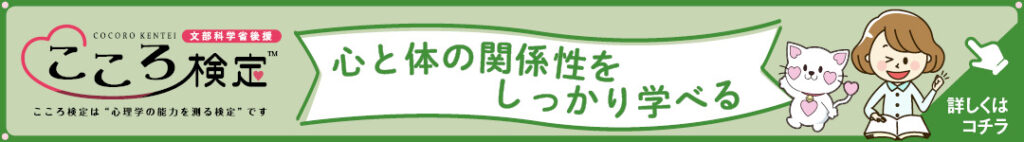
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo