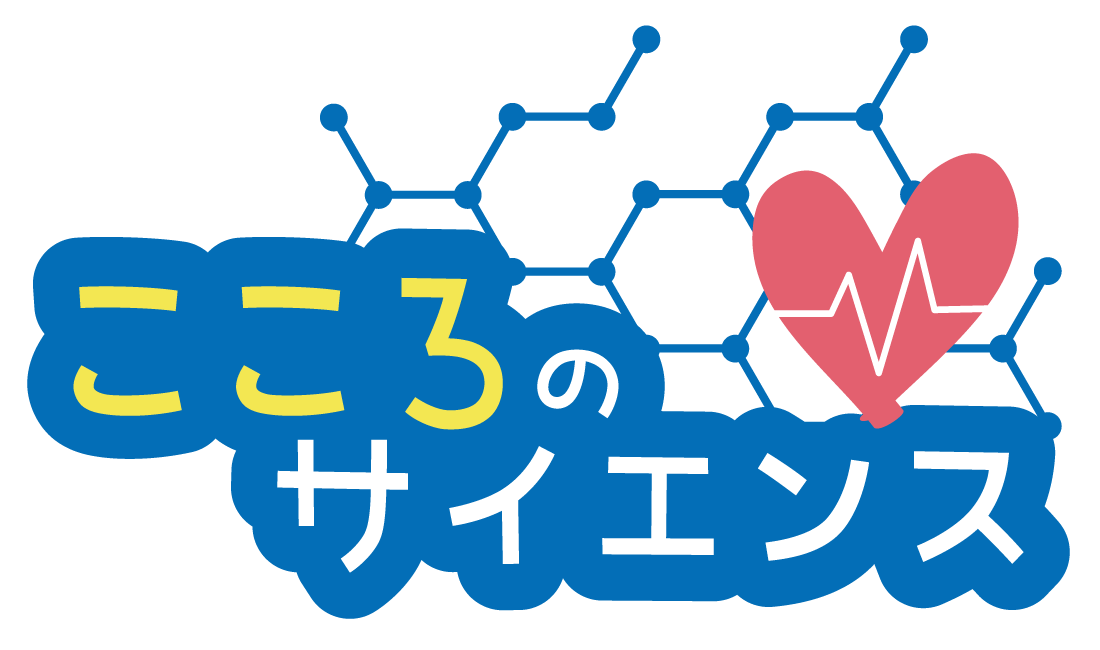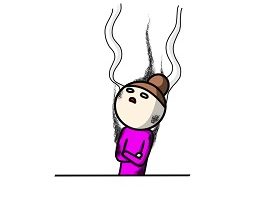体内時計の日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
3月31日は「体内時計の日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。3月31日は「体内時計の日」に制定されています。これは、ドコモ・ヘルスケア株式会社が制定したもので、日付は入社や入学などの新生活の変わり目に生活リズムを省みる日として、新年度が始まる前日の3月31日としています。
ちなみに、体内時計とは、一日のリズムに沿って、血管や臓器の働きを調整する自律神経やホルモンの分泌などをコントロールする身体の司令塔の役割を果たしているものです。朝に太陽の光を浴びることや、食・睡眠を整えると、体内時計の機能が高まり、ダイエットやアンチエイジングの効果アップや、生活習慣病の予防にもつながるとされています。
では、体内時計と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
生理心理学における時間について
時間については、心理学において、生理心理学や認知心理学などの分野で研究が進められています。また、最近では、様々な時間に関する学術的な研究を体系化して、時間学という学問分野も確立されています。
生理心理学において、人間の身体には目や耳などの感覚器官がありますが、時間を光や音のような刺激として受け取ったりする器官は存在しないことが明らかになっています。しかし、人間は1 年、2 年といった長期間から5 秒といった短期間までの様々な時間を感覚として把握することができます。これは人間が複数の器官のメカニズムを併用して時間の感覚を得ているからです。人間の身体は約24 時間のサイクルで脳波や体温、血圧などが規則的に変化します。このような約24 時間周期で身体に規則的な生理変化が発生することを概日リズム(サーカディアンリズム)とよびます。
海外旅行などで発生する“時差ぼけ”は、概日リズム(サーカディアンリズム)による身体内の状態と外界の状態の不一致から生じるものです。そして、この概日リズム(サーカディアンリズム)こそが、体内時計のことであるということになります。概日リズム(サーカディアンリズム)は脳の視床上部にある松果体から分泌されるメラトニンというホルモンによって制御されています。メラトニンの分泌は夜間に多くなり、昼間は減少します。より厳密にいえば、起床から約14 時間後にメラトニンの分泌が開始されます。つまり、仮に朝7 時に起床したとすると、夜の9 時ころにメラトニンの分泌が開始され、それが「夜である・眠りにつく段階である」という合図となって、徐々に睡眠・休息へと身体各部位に生理的変化が起こります。また、メラトニンの分泌は光を投射されると抑制されるという特徴があります。
そのため、夜間には存在しなかった太陽や照明の光を浴びることで、メラトニンの分泌が減少し、それが「朝昼である・活動する段階である」という合図となって、徐々に覚醒・活動へと身体各部位に生理的変化が起きるのです。昼は仕事、夜は睡眠という生活を送っているにも関わらず、夜にあまり眠れず、逆に昼はボーっとしてしまうということがあるかと思います。それは夜間に不必要な光刺激に曝されてメラトニンの分泌が抑制され、概日リズムに影響が出たということが原因の1つとして考えられます。
また、生理心理学における研究により、人間は体温が高い時は実際よりも時間を速く感じ、逆に体温が低い時は実際よりも時間を遅く感じる傾向があることが分っています。時間に関しては認知心理学の観点からも研究がされており、認知的な負荷が高い時(複雑・困難な作業や課題実施時)は、実際よりも時間を長く感じ、逆に認知的な負荷が低い時(単純・平易な作業や課題実施時)は実際よりも時間を短く感じる傾向があることが判明しています。
最後に
このように、心理学では、時間についても、様々な角度から研究が実施されているのです。
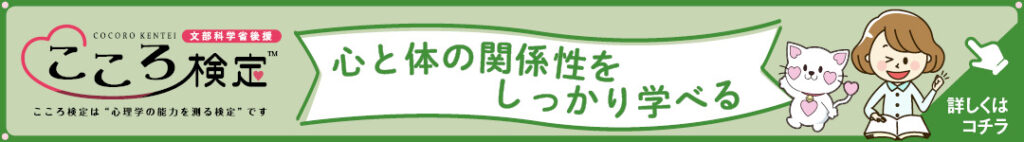
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo