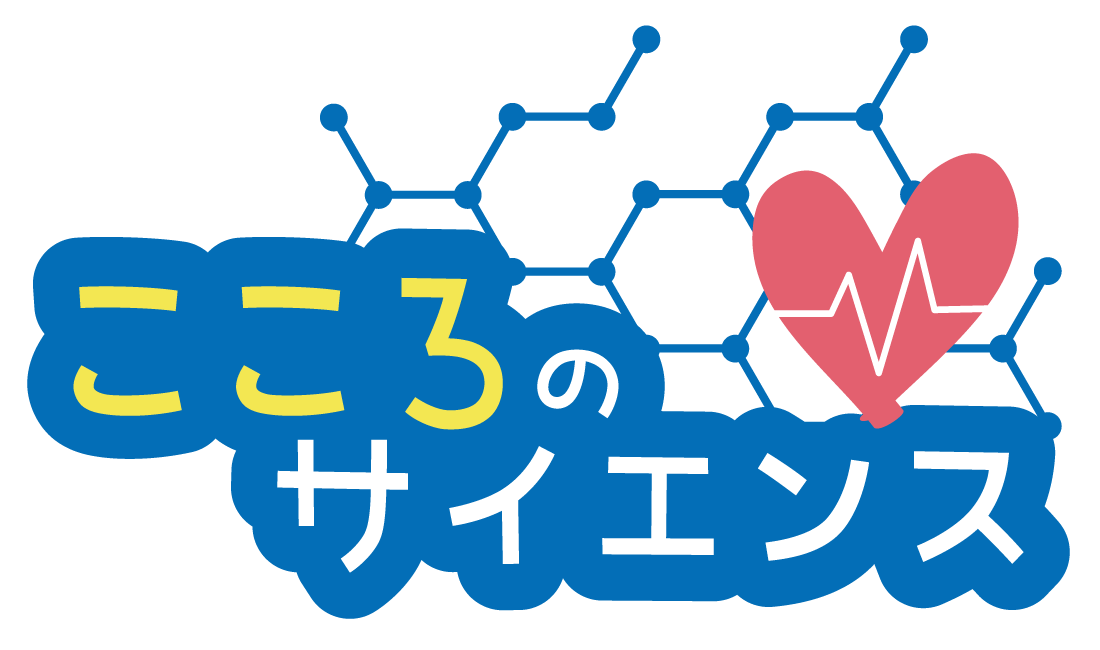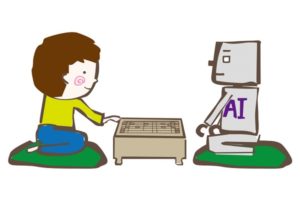世界観光の日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
9月27日は「世界観光の日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。9月27日は「世界観光の日」に制定されています。これは世界観光機関(World Tourism Organization:WTO)が制定した国際デーの一つです。1979年9月にスペインのトレモリノス市で開催された世界観光機関の第3回総会で翌年の1980年から「世界観光の日」を制定することが決議されました。そこで、改めて観光の歴史を振り返り、世界観光機関憲章が採択され、世界の観光における重要な節目となった1970年9月27日をきっかけとして、9月27日を記念日として制定しています。
では、観光と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
観光の裏にある“感情”を読み解く心理学
心理学の一分野に産業・組織心理学というものがあります。そして、この産業・組織心理学の中に観光心理学という分野があります。観光心理学では、人間がなぜ旅行をしたいと思うのか、旅行においてどんな体験を求めているのか、旅行中にどんな気持ちになるのか、旅行が終わった後に何を感じるのかといった、観光に関わる人間の心理的過程について研究することを主な目的としています。
まず、最も根本的な疑問として、人間はなぜ、旅行をするのかというものですが、観光心理学では、ストレス軽減(リラックス)、新規の経験・体験などから知的好奇心を満たす、自己成長や自己実現、社会的関係性(コミュニケーション)などが主な理由として挙げています。いずれも、これらの理由をきっかけとして何らかの満足感を得るということが旅行・観光の目的であると考えられます。観光心理学では観光における満足について、期待と現実のギャップ、フロー体験(何かに夢中になって時間を忘れて楽しむなどの没頭体験)、感情の記憶などの要素が重要であるとしています。 観光心理学の研究成果は様々な場面で活用されています。たとえば、観光地のプロモーション活動が挙げられます。観光地がSNSでいわゆる「映える」写真を発信することで、特に若者の共感や感情に影響を与えることができます。感情を揺さぶり、共感を得ることによって、多数の観光地の中から選ばれやすくなるというマーケティング的な要素があるわけです。また、地域活性化も観光心理学の研究成果が活かされる場面の1つです。観光客がまた来たいと思う(リピーターになる)ようにするにためには、どのようなアプローチが必要になるのかということは非常に重要です。そのため、感動できる体験や観光地ならではの他者との心温まる交流が大きなポイントとなります。地元の人との触れ合いや伝統文化を体験することが満足感を高めることにつながり、リピーターを生み出すきっかけとなると考えられています。
観光心理学は、暮らしと世界をつなぐ知
このように観光心理学の知見は観光業だけでなく、地域振興や宣伝広告、イベントの企画、国際交流などの様々な分野で活用されているのです。
日本ではまだ観光心理学が盛んに研究されているわけではありませんが、関連する学術団体は存在しています。観光心理学についても研究のメインの1つとしているものとして、余暇ツーリズム学会があります。余暇ツーリズム学会は余暇学と観光学という2つの学問の観点から、多様な人間の活動や状態に関して総合的にかつ多角的に研究・検討するためことを目的としています。労働と余暇が明確に区別されるようになったのは近代以降のことであるとされています。つまり、心理学においても産業・組織心理学が誕生したことで、労働を心理学的に研究するようになったわけですが、さらにそこから労働と休息を除いた、ライフスタイルの重要な要素である余暇にもスポットライトが当たるようになったのです。そして、もう1つ重要なのが旅、ツーリズムというものです。ツーリズムもまた近代以降に誕生・発展し、現在は1つの産業になっています。
最後に
このように、観光心理学は学問としても、ビジネス応用としても、注目を集めている新しい分野なのです。
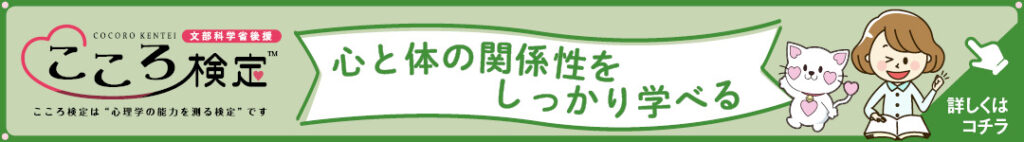
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo