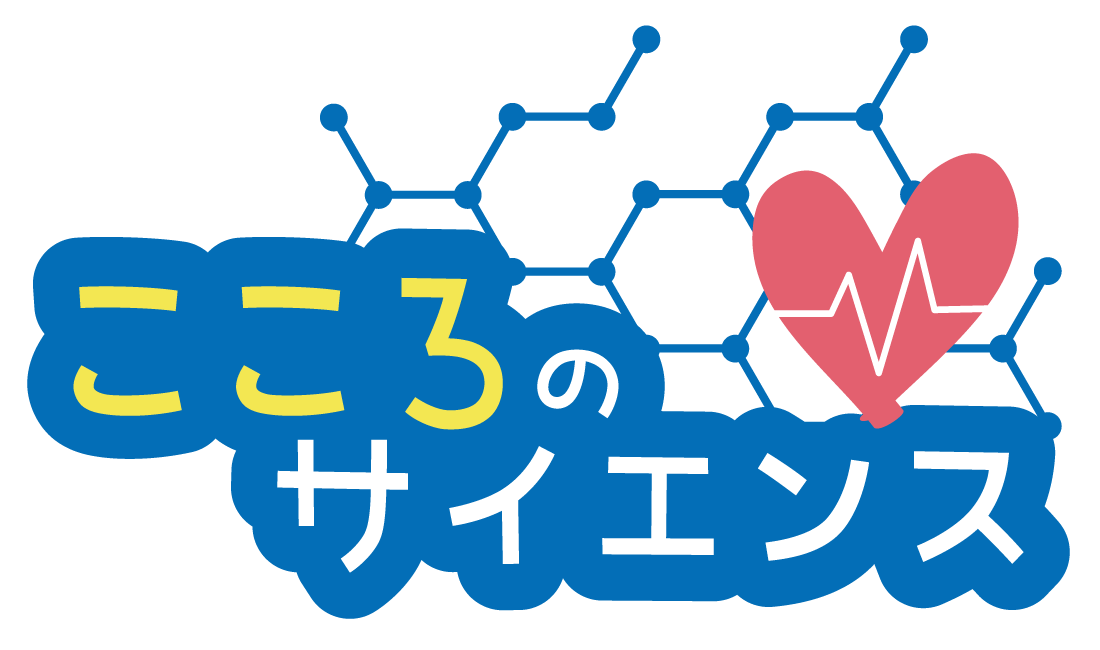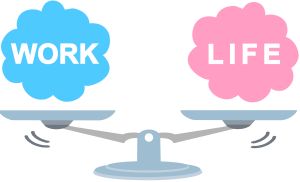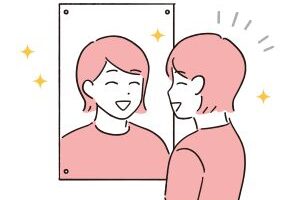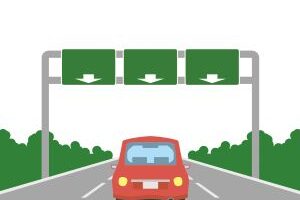東京大学創立記念日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
4月12日は「東京大学創立記念日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。4月12日は「東京大学創立記念日」に制定されています。これは、1877年4月12日東京開成学校と東京医学校を併合して東京大学が開設されたことが由来です。東京大学は欧米諸国の諸制度に倣い、日本国内で初の近代的な大学として設立され、法学部・理学部・文学部・医学部の4学部が設置されました。1897年に東京帝国大学に改称され、さらに戦後の1947年に再び東京大学に改称されています。
現在、東京大学は本郷・駒場・柏・白金・中野の5つのキャンパスがあります。また、本郷キャンパスの校門の一つとして赤門が有名ですが、これは1931年に国の重要文化財に登録されています。同じく、東京大学で有名なのが安田講堂ですが、これは安田財閥の創始者である安田善次郎が匿名を条件での寄付により建設したものです。安田の死後に寄付のことが知られるようになり、安田を偲んで一般に安田講堂と呼ばれるようになりました。
では、東京大学と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
元良 勇次郎 先生
日本の心理学者には東京大学(当時の東京帝国大学)の出身の先生方がいます。元良勇次郎は安政5年11月1日(旧暦:新暦では12月5日)生まれの日本の心理学者です。兵庫県に生まれた元良は、まだ若いころにアメリカに渡り、ジョンズ・ホプキンズ大学でホールから指導を受けます。ホールとは、ジョンズ・ホプキンズ大学の教授やクラーク大学の総長を務め、1892年にはアメリカ心理学会(APA)の設立および初代会長に就任した人物です。ホールはアメリカの心理学界の組織化に尽力し、研究においては、教育・児童・青年・老年・宗教など新しい領域を開拓し、アメリカにおける応用心理学領域では最も著名な心理学者の1人です。そんなホールの下で研究に従事した元良は1888年に“Exchange : Considered as the principle of social life”というテーマで博士論文を書き、博士号を取得しました。同年、東京帝国大学(現在の東京大学)で初めて精神物理学の講義を実施しました。また、1890年には、東京帝国大学の初代心理学教授となりました。
内田 勇三郎 先生
内田勇三郎は1894年12月15日生まれの日本の心理学者です。内田は1921年に東京帝国大学(現在の東京大学)の心理学科を卒業し、その年に財団法人 協調会産業能率研究所で働きはじめます。「産業能率」という言葉が示す通り、この法人は産業・組織心理学に関連する研究所であり、人間のパーソナリティ(性格)の傾向と職業や職種との関係についての内田の研究が重要な役割を担っています。それが、後の内田-クレペリン精神作業検査の開発につながっていきます。
佐久間 鼎 先生
佐久間鼎は1888年9月7日生まれの日本の心理学者・言語学者です。千葉県で生まれた佐久間は、1913年に東京帝国大学(現在の東京大学)の文学部を卒業し、1923年に文学の博士号を取得しました。佐久間はドイツに留学し、ベルリン大学でケーラーの指導の下で、ゲシュタルト心理学を学び、帰国後にゲシュタルト心理学を日本に紹介し、その普及に努めました。また、ゲシュタルト心理学における場の概念を言語学の分野に応用し、独創的な日本語指示詞の「コソアド論」を提唱しました。さらに、佐久間は禅の心理学的研究にも関心を示しました。そのため、1968年には駒澤大学で教授を務めました。1925年に九州帝国大学(現在の九州大学)の初代の心理学講座担任教授を務めました。1949年に九州帝国大学を退官し、1952年に東洋大学の教授として、心理学と国語学を担当し、1960から1963年までの3年間、東洋大学の学長も務めました。佐久間は心理学者・言語学者としての功績が評価され、1965年に紫綬褒章を授与され、1966年には日本学士院会員に選ばれました。
最後に
このように、東京大学出身の心理学者は、日本の心理学の草創期を支える重要な研究を多く実施しているのです。
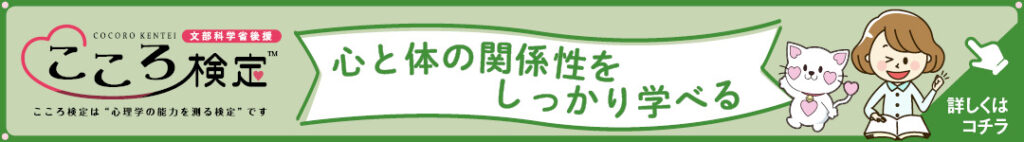
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo