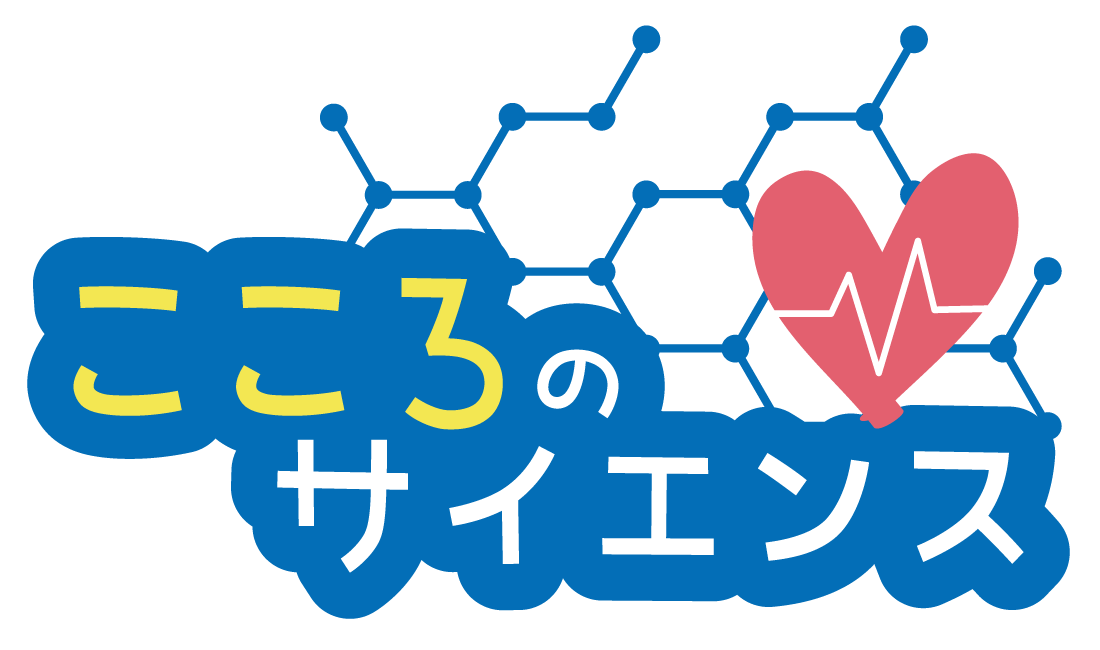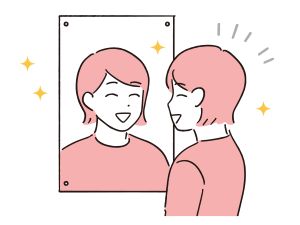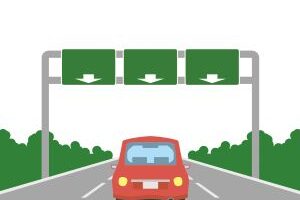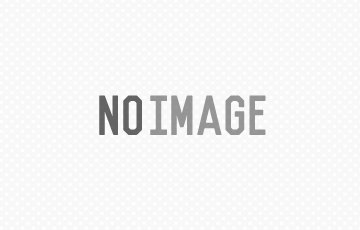鏡の日と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
11月30日は「鏡の日」
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。11月30日は「鏡の日」に制定されています。これは「いい(11)ミラー(30)」の語呂合わせが日付の由来となっており、鏡を大切にして、健康で美しい生活を目指すことを目的としています。なお、11月11日も「鏡の日」となっており、この記念日については鏡を扱う業界団体の全日本鏡連合会が制定した記念日です。日付の由来は「11 11」や漢字の「十一 十一」を縦書きにした文字が鏡に映したように左右対称であるからとなっています。
では、鏡と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
鏡については、心理学の実験や専門用語して、関連するものがいくつかあります。そこで、本コラムではその中からいくつか紹介していきたいと思います。
鏡映色
鏡映色とは生理学者・心理学者のカッツが分類・記述した色の現れ方の一つです。鏡映色は鏡のように光を反射する面に映った物体の色のことを指します。たとえば、静かな湖面に映し出された風景の色などが鏡映色の代表例です。
鏡映書字
鏡映書字とは、字を書く時に鏡に映したように、ひっくりかえった文字を書くことを指します。鏡映文字は、別名、鏡文字・鏡像文字・逆文字・裏文字などともよばれることがあります。また、文字だけでなく、非対称形をした図形を描く時にも発生することがあります。幼児期に鏡映文字を書くことは発達的にごく正常な現象であるとされています。幼児期の鏡映書字の現象は自他の左右認識の未分化や利き手の未分化ということと時期的に重なっており、原因として大脳の左右半球の機能分化の問題と密接に関連するといわれています。さらに、鏡映書字は書くという動作に問題があるのではなく、むしろ文字の認知の問題であり、認知発達が関係していると考えられています。鏡映文字に関する実験では、5~6歳児では文字・図形ともに鏡映を類同視する反応が最も多いものの、7~8歳頃から45°回転を類同視する反応が増加し、文字では6歳と7歳の間で図形では7歳と8歳の間で類同視の対象が鏡映から45°回転へと移行することが明らかになっています。つまり、幼児期にはまだ、特定の文字・図形とその鏡映像との認知的な区別がついていない状態であるということになります。なお、鏡映書字は幼児期だけでなく、老年期にも認められる場合があり、さらには脳の左半球の損傷患者においても鏡映文字の出現頻度が高いことが分かっています。やはりこれも、加齢や損傷による認知機能の問題が関係していると考えられます。
鏡映描写装置
鏡映描写装置とは、鏡を利用することによって、文字や図を上下あるいは左右に反転させて鏡映像として呈示し、それを刺激として文字や図を描写するための装置のことです。一般的には星型などの図形を用いて、知覚 = 運動学習や練習効果の転移に関する実験に多く使用されています。実験参加者は鏡映図形を見ながら描写することになりますが、上下や左右に反転されているので、学習の初期には強い注意の集中が必要となります。
鏡映的自己
鏡映的自己とは社会的自己に関して、心理学者のクーリーが提唱した概念です。鏡映的自己とは、他者の自分に対する言動や態度を手がかりとして、自分という人間が他者にどう思われているかを推測し、それに基づいて作りあげた「自分はどんな人間なのか?」についての理解のことを指します。鏡映的自己はまるで他者を鏡のように見なし、そこに映った自分の像から自己の特徴や状態を知ることであると定義されています。
鏡像段階
鏡像的段階とは、精神分析の専門家であるラカンが乳児が自己鏡像を初めて認知するに至る過程に対して考え出した概念です。ラカンは乳児は最初に自分の全体像を知らない「分断された身体」あるいは「漠然とした衝動の塊」として生きていると述べています。それが生後6カ月頃から18カ月頃にかけて、鏡に映る自分の姿との戯れ・関わりを通して、徐々にそれが紛れもない自分(の虚像)であることに気づき(同一化機能の始まり)、また、自分の可視的・客体的全体像を把握するようになるとしています。これは、自己意識や自我の萌芽を示すものと考えられています。
最後に
このように、鏡というキーワードについても、心理学では様々な角度から研究が進められています。
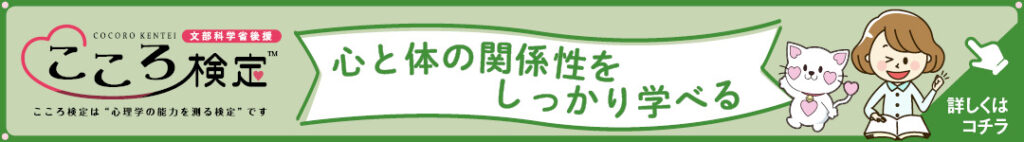
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @cocorokeninfo